
2025.01.17
ESG
レジリエンス
サスティナビリティ
備え・防災アドバイザー 高荷智也氏に聞く
レジリエンスを高め、持続的成長につなげる
オフィス防災対策
災害大国ニッポン――昨今、多くの企業で自然災害や予期せぬ緊急事態への備えとして、飲料水や食料品の備蓄が行われています。こうした従業員の「命」を守る対策に加え、企業としては「事業」を守る準備も不可欠です。今回の「Think!OFFICE」では、防災の専門家である高荷智也氏に、BCPの策定手法や実行に必要な防災備蓄品の備え、オフィス選定の際に必要な視点など聞きました。
「自分と家族が死なないための防災対策」と「企業の実践的BCP策定」のポイントをロジカルに解説。堅い防災を分かりやすく伝えるアドバイスに定評があり、講演・執筆・コンサルティング・メディア出演など実績多数。

- 備え・防災アドバイザー/BCP策定アドバイザー
- 高荷智也(たかに ともや)
自社が災害に見舞われるリスクを想定する
―― BCP策定のポイントについて教えてください。
まずは従業員や施設来場者など、そこにいる人々の命を守る対策を行い、その上で事業継続に必要な対策をしていくことが、BCPの大前提。BCP策定では、被害を減らすための「防災対策」と、被害が起こることを前提とした「代替計画」の二つを準備する必要があります。
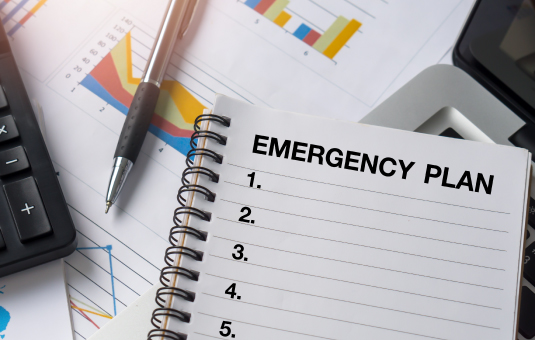
①被害を減らすための「防災対策」
災害が発生した場合に備え、人や建物、設備、情報など自社が持つ経営資源を守る取り組みです。まずは、自社が災害に見舞われるリスクを想定することが重要。
・地震への対策
建物の耐震化や什器の固定など室内の安全対策を実施する。
火災発生に備えた消防計画の作成、定期的な防火訓練などを実施する。
・水害への対策
国交省の「重ねるハザードマップ」をWEBで確認し、拠点周辺の水害リスクを把握する。
※住所を入力すれば、全国任意の地点のハザードマップをシームレスな地図で閲覧可能です。
拠点が浸水する高さにある場合は、止水版の用意、車両や設備の移動の準備、沈まない高さへのフロア移転などが具体的な対策となります。
②被害が起こることを前提とした代替計画
災害等により事業継続に不可欠なものが使用できなくなった場合に備えるものです。
・社内の経営資源を複数の拠点に分散させる
・予備の車両や設備を用意しておく、情報は自社サーバー以外にクラウド等を使って分散管理しておく
・取引先やパートナーが被災する場合も考え、普段から在庫を持つ、複数の仕入れルートを確保する
・事業継続に必要な電気や水の確保、非常用トイレの準備といったライフラインを代替する備品を用意しておく
ただ、災害が起こるとすべての事業を維持することができない恐れもあり、「選択と集中」も必要。会社としての優先順位を考え、対応を決めておく必要があります。
―― 新築のオフィスビルでは非常用発電機を備えているところも。自社での準備は必要ないのでは?
多くの場合、オフィスビル管理者側で備えている非常用電源は、エレベーターやトイレなど共有部分への電源供給を想定しており、各企業が使用する電気は個別確保が必要です。ただ、最近は専有部分にも電力供給をするビルも出てきています。その際は、ビル管理者側の対策をヒアリングしたうえで、必要な備えを行いましょう。
普段使いのウォーターサーバーや置き菓子も備蓄品として活用できる
―― 水や食料品など防災備蓄品は、何をどの程度用意する必要がありますか。

現在は、都市部で大規模災害が発生した場合、3日間(72時間)はむやみに移動せず、安全な場所にとどまるよう国のガイドラインで定められています。大震災などが生じた場合、発災直後の屋外は危険な状況となり、徒歩帰宅をすると命を落とす恐れがあります。また発災直後の72時間は人命救助が最優先ですが、徒歩帰宅者が車道をふさぐと緊急車両が通行出来なくなり救助活動が止まります。周囲の安全が確認されるまで、その場に留まることが重要です。
事業者としては滞在のための3日分の防災備蓄品を準備しておく必要があります。備蓄品の中身は水や食料、非常用トイレ、マットや毛布といった寝るための道具などで、基本的には出社している人数×3日分プラス予備(10%程度)が目安の数量になります。加えて、災害時には家族との安否確認が非常に重要になりますので、スマートフォンを作動させるための乾電池式充電器やポータブル電源なども備えておきましょう。
備蓄品を用意する方法として、例えば水や食料であれば、ウォーターサーバーや自販機、お菓子や惣菜置き場などを設置するのも有効です。普段使いでき、福利厚生の一環にもなるのでお勧めです。
建物の耐震性に加え、周囲の環境も把握する
―― BCPを意識したオフィスビルの選び方を教えてください。
命を守る防災でも、事業を守るBCPでも、拠点を維持することが要になるので、建物を守る行為は最重要事項の一つです。
建物の地震対策としては効果の高いものから順に、建物を揺らさない「免震」、揺れを小さくする「制振」、通常の耐震基準に適合した「耐震」の三つがあります。効果が高いのは「免震」ですので、可能なら「免震」の建物を選ぶことでリスクを軽減できます。また「制振」は高層ビルなどに適用されている技術で、揺れはしますが致命的な損害には至らないというもの。ただし「耐震」物件同様、揺れはありますので家具や什器の固定といった対策は必要になります。
火災・水害対策に関しては、建物設備はもとより立地が重要です。例えば木造住宅が密集している地域は、大規模な延焼火災の恐れがありますので、できればこうした立地は避けること。東京都なら地震火災に関するハザードマップを公開しているので、こうした情報を参考にするのも良いでしょう。
水害については、ハザードマップ等を確認し、津波、洪水、高潮、土砂災害などの影響がない場所を選んでいただくか、影響が生じない高さの物件を選んでいただくことが重要です。

新耐震基準の物件を選ぶ際にも注意が必要
―― 築古物件を選ぶ際のポイントや、行うべき対策を教えてください。

1981年6月1日に法律が改正され耐震基準が見直されていますので、古い物件でもこの日よりも後に建築確認を受けている物件は、最低限、新耐震基準に沿っています。こうした物件を選んでいただくことが一つ。ただ新耐震基準とはいえ初期から40年以上経っていますので、経年劣化等で耐震性が弱くなっている恐れもあります。改修や管理の状況などにも注意が必要です。
それよりも前に建築確認を受けている旧耐震基準の建物に関しては、震度6強の直撃を受けると1回目の揺れで、倒壊する危険性がありますので、耐震改修が行われているかどうかを必ず確認し、耐震性に問題がなければ入居、そうでなければ避けるのが正しい選択といえます。
もう一つ物件選びのポイントとしては、2000年4月1日にスタートした住宅性能表示制度があります。これは国の耐震基準とは別の耐震等級で、レベル1~3の3段階で表示されます。住宅とありますが一定以上の大きさの建物が任意で取得できるものです。一番頑丈な耐震等級3の建物は、これまで倒壊したことは一度もなく、震度6強や震度7の直撃を連続で受けても基本的にはほぼ被害のない建物です。築古でも築20年より新しい建物であれば、この耐震等級が導入されている可能性があるので、選ぶ際の一つの目安になります。
誰が防災対策を行うかを明確に
―― シェアオフィスでの勤務やリモートワークなど働き方が多様化するなか、BCP対策で気を付けておくべきポイントを教えてください。
建物や室内の防災対策を誰がするのかがポイントになります。建物選びに関しては、シェアオフィスでチェックするべき点も自社オフィスと同じです。一つ違うのは、シェアオフィスの場合は備蓄品を誰が準備するか。施設側で特に準備がない場合は自分たちで用意する必要がありますので、まずは現状をオーナー側と確認してください。
一方リモートワークの場合は、自宅の防災です。これは従業員それぞれがやることなので、防災意識を啓蒙するしか手はありません。ただその際の方法が重要です。例えば自宅の防災チェックリストを会社で作成し、必要な対策が施されている人にはリモートワーク手当を増額するなど、金銭やインセンティブを使って啓蒙するといった手法は有効だと思います。
加えて、リモートワークが一般的になり、災害が起こった時に総務部や防災担当者が出社しているとは限りません。発災時の緊急対応については、対応策をマニュアルにまとめる、備蓄品の場所を事前に共有しておくことが大切です。
また安否確認についても、本人、家族が無事かどうかの連絡に加え、その人が出社できるのか否か、難しいのであればいつ頃出社できるのか、あるいはまったく見当がつかないのかなど、状況を合わせて報告する体制が必要です。建物や設備同様、人という経営資源の状況を把握することも、BCP対策にとって重要であることを覚えておいてください。
―― 最後に 関電不動産開発は企業活動のステージとなるオフィスの快適・安全・安心基盤を提供するデベロッパーとして、今求められているオフィスづくりに邁進します。
淀屋橋駅西地区市街地再開発事業|2025年12月竣工予定
https://yodoyabashi-west-project.jp/
大阪のメインストリート「御堂筋」の玄関口に誕生する、地上29階、オフィス&商業の大型複合ビル。
災害などに強い建築・設備計画とし、非常時にも企業活動を守るBCP(事業継続計画)対策を充実させています。

